| ■第23回農業土木新技術検討報告会(3課題) 開催日 平成18年10月31日 |
| ■第22回農業土木新技術検討報告会(2課題) 開催日 平成17年11月1日 |
| ■第21回農業土木新技術検討報告会(2課題) 開催日 平成16年10月28日 |
| ■第13回環境測定技術研究会発表会(1課題) 開催日 平成16年6月23日 |
| ■第23回農業土木新技術検討報告会 (開催日 平成18年10月31日) | |
|
『草地における低コスト疎水材型無管暗渠の効果検証及び |
|
|
根室支庁産業振興部農村振興課
(財)北海道農業近代化技術研究センター |
中川 隆 ○内門 亮子 南部 雄二 山崎 祐樹 |
| 【講演の概要】 牧草は収益性が低く暗渠の費用対効果も低いことから、草地帯では暗渠排水が普及していない。しかし、排水性の悪いほ場は機械作業が遅れ、牧草の収量、品質も低下することから排水改良は必要であり、低コストな暗渠工法の開発が求められてきた。草地帯に適した低コスト工法を確立するため、次のとおり検証を行った。 試験ほ場にて、無管暗渠区(疎水材のみ)と完全暗渠区(管を埋設し疎水材を投入)を設け、降雨後の排水量、地下水位の状況を観測し、無管暗渠区でも完全暗渠区と同等程度の排水機能を有することを確認する。 また、草地帯は家畜ふん尿による河川環境への配慮も必要であることから、疎水材の水質浄化機能にも着目した。無管暗渠の断面モデル装置を使い、スラリー溶液の浄化試験を行った。分析項目はT-N、T-P、NH4-N、NO3-N、大腸菌郡数等全8項目とし、散布前の数値と比較した。 |
|
| ■第23回農業土木新技術検討報告会 (開催日 平成18年10月31日) | |
|
『トラフ浮上対策について(最終報告)』 |
|
|
根室支庁産業振興部農務課
空知支庁北部耕地出張所 (財)北海道農業近代化技術研究センター |
田村 顕仁 千葉 貴統詞 ○ 梅沢 直仁 |
| 【講演の概要】 現在、北海道農業の近代化に合わせ、ほ場の大区画化や用排施設を始めとした農業施設の整備を進めている。 この中で、比較的規模の大きい用水路においては、「浮力」による浮上被害が発生しており平成13年度より調査研究を行ってきたところである。 前回(平成16年度)は、実証室内実験及び検証室内実験等から浮上発生メカニズムの解析と対策工の検討及び考察、更には一連のマニュアル(案)の作成までを行い中間報告を行った。 今回は、最終報告ということで浮上対策工法を用いた現地実験とその効果検証を踏まえたマニュアル(案)の策定までを報告する。 |
|
| ■第23回農業土木新技術検討報告会 (開催日 平成18年10月31日) | |
|
『多孔管方式が混在する地域の畑地灌漑用水利用モデルの適正化』 |
|
| 北海道後志支庁産業振興部農村振興課 赤井川村産業建設課 (財)北海道農業近代化技術研究センター |
打田 彰雄 菅原 誠二 原 智之 ○ 山崎 祐樹 南部 雄二 |
| 【講演の概要】 赤井川地区は、畑地灌漑施設の整備に伴う用水利用により、露地・ハウス栽培での高収益作物が導入されている。本地区はリールマシンによる灌水が想定されていたが、高収益作物導入による集約化に対応した灌水方式である多孔管(露地・ハウス)も導入している。しかし、多孔管灌漑では、きめ細かな水管理が求められる一方で、灌水時間帯が集中するなど、配水計画上の用水利用と異なることが想定される。 本調査では、現地での露地栽培・ハウス栽培における用水利用実態を把握し、課題点を明確にしたうえで改善策を検討し、用水利用改善状況について検証した。その結果、ローテーションブロック内で利用調整することで、改善可能であることが実証された。 |
|
| ページTOPへ |
| ■第22回農業土木新技術検討報告会 (開催日 平成17年11月1日) | |
| 畑地かんがい施設整備による地域営農の変化 〜石狩市高岡地域の事例〜 |
|
|
北海道石狩支庁農業振興部整備課
(財)北海道農業近代化技術研究センター |
菅井 徹 ○小林 英徳 南部 雄二 |
| 【講演の概要】 石狩市北部の高台丘陵地に位置する高岡地域では、稲作を主体に、畑作・露地野菜作、施設栽培を取り入れた複合経営が展開されている。これまで、地域の水源は素掘りの皿溜や地下水に依存していたため、安定的で良質な用水を確保することは難しく、特に干ばつ年での用水確保には多大な労力を要していた。 このため、国営かんがい排水事業高岡シップおよび道営緊急畑総事業高岡地区により畑地かんがい用水を確保し、ほ場かん水施設が導入された。地域では、畑地かんがい施設の整備を契機に、施設栽培の生産組合が発足し、高収益作物導入による営農の転換が図られている。 本報告では、畑地かんがい施設整備による地域営農の変化、生産者の評価、出荷農作物の市場評価等について検証し、施設整備効果が発現する条件について考察する。 |
|
| 【考察と評価の概要】 従来、施設園芸に特化した地域ではなかった高岡地域において、かんがい用水が確保され、集約型作物と土地利用型作物の方向性が明確となり、集約型農業においてはミニトマトを主体としたハウス栽培が拡大し、生産性の安定、収益性の向上等、地域営農の変化がみられた。 また、都市近郊の立地を活かした施設園芸を拡大するための施策と労働力を確保するための施策の相乗効果により、かんがい用水を利用した営農形態が定着しつつある。 このように、畑地かんがい施設の導入により、個々の営農の変化と地区内の営農の変化がみられ、施設整備は地区特性に応じた営農目標を設定し、着実に実践していくための生産基盤となり、その重要性が示された。 また、かんがい用水の安定的な確保と用水利用の利便性向上は、将来的にも導入作物の選択肢を拡大し、後継者・新規就農者の確保にも明るい兆しを感じる材料となり、精神面での評価も高いものである。 さらに、地域の農業振興計画との関係性からも、地域における明確な位置付けが読み取れ、畑地かんがい施設の有効性とその効果をみることができた。 これらの効果は、地域農業の活性化に向けた畑地帯総合整備事業および畑地かんがい施設導入による成果と評価できる。 今後、畑地かんがい施設を整備していく地域において、地域農業との関わりを明確にし、地域農業の新たな戦略の一つとして、かんがい用水の活用を位置付けていくことが望まれる。また、地域特性に対応した、かんがい技術の確立とその普及が、施設整備効果を確実に発現させるうえで重要な要素となる。 |
|
| ページTOPへ |
| ■第21回農業土木新技術検討報告会 (開催日 平成16年10月28日) | |
| トラフ浮上対策について | |
|
北海道空知支庁北部耕地出張所
(財)北海道農業近代化技術研究センター |
田村 顕仁 千葉貴統詞 ○梅沢 直仁 |
| 【講演の概要】 作物の増収や品質の向上、さらには生産コストの低減等を図るため、各種施策・整備対応が図られている。農業・農村整備事業のほ場整備においても大区画化、用排水路の整備等が進められており、事業実施にあたっては、建設コストの縮減、安全性確保の観点から計画設計に係わる諸種の基準、指針等の改訂が進められている。 一方、多様な現場条件に対し、指針のみの対応では充分対応しきれない場合も見られ、近年水路施設の水路においては、施工後に「浮力」による水路構造物浮上被害が発生しており、施設管理者は維持管理・補修等に多大な労力を費やしている実態がある。 本調査研究は平成13年度からの継続研究であり、平成16年度内に指針に反映させるためのマニュアルの作成を目的としており、本報告はトラフ用水路に対する平成14年度までの研究成果を中間報告としてとりまとめたものである。 |
|
−研究概要− |
|
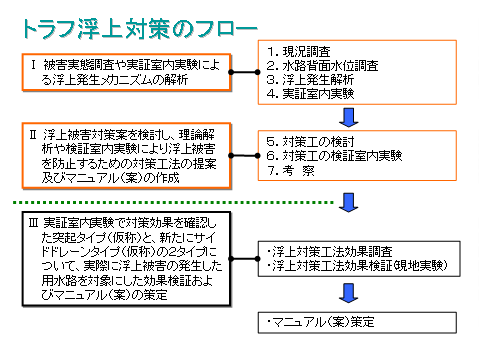 |
|
| ■第21回農業土木新技術検討報告会 (開催日 平成16年10月28日) | |
| 農業農村整備事業地区管理システムの開発と普及にむけて | |
|
北海道空知支庁北部耕地出張所
北海道網走支庁東部耕地出張所 北海道後志支庁農業振興部整備課 (財)北海道農業近代化技術研究センター |
○南部 雄二 飛田 米雄 |
| 【講演の概要】 各地域で整備されている農地に係る情報の有効利用を図り、将来的にも利用可能な情報を地理情報システム(GIS)として構築することは、農業農村整備事業を効率的に実施していくうえでも有効的な手段である。 北海道農政部では、計画樹立から事業完了までの過程で、計画変更も含めた事業管理の効率化を図ることを目的に、GISによる農業農村整備事業地区管理システムを開発してきた。平成15年度は、平成14年度までに開発した基本システム(Ver3)に、①CADデータの取り込み、②図書管理、③施設管理などの機能を追加し、機能充実と利便性の向上を図った(Ver4)。 本報告では、システムの基本機能、データ構築の事例、今後の利用展開にむけた方向性についてとりまとめた。 |
|
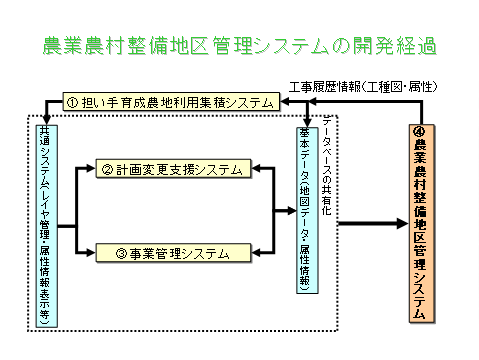 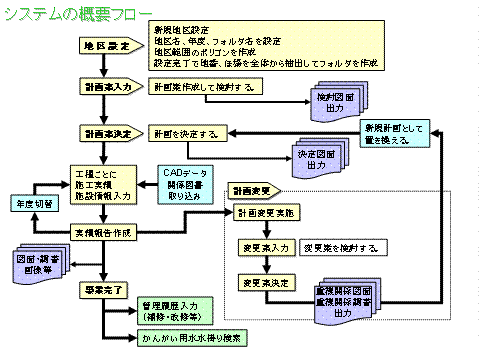 |
|
| ページTOPへ |
| ■第13回環境測定技術研究会発表会 (開催日 平成16年6月23日) 主催:(社)日本環境測定分析協会北海道支部 北海道環境計量証明事業協議会 |
|
| 融雪水影響調査研究 〜積雪に含まれる酸性成分の挙動と土壌への影響〜 |
|
|
(財)北海道農業近代化技術研究センター
|
○田中 雅文 |
| 【講演の概要】 本研究では、道内でも降雪量の多い深川市において、その基幹産業である水稲栽培を支える水田(試験ほ場)における積雪中の酸性成分を中心に調査を行った。特に融雪期のこれら成分の挙動を把握するため、深さ方向の濃度プロファイルがどのように変化するかを調べ、土壌との相互作用を把握することを試みた。なお、バックグラウンドのデータとして降水(雨、雪)中の各化学成分濃度についても調査を行った。 アシッドショックに関する基礎データを得るために、深川市の降水及び積雪の化学成分について調査を行った。この結果、融雪期には短期間に各成分の濃度は半減し、下層へ移行していることが推定され、アシッドショックのメカニズムに合致する現象が確認された。しかし、pHは融雪期の最下層で7前後になることから、酸性化は土壌成分の溶出などにより抑制されているものと推測される。今後は種々の土壌について同様な調査を行う必要がある。 |
|
| ページTOPへ |